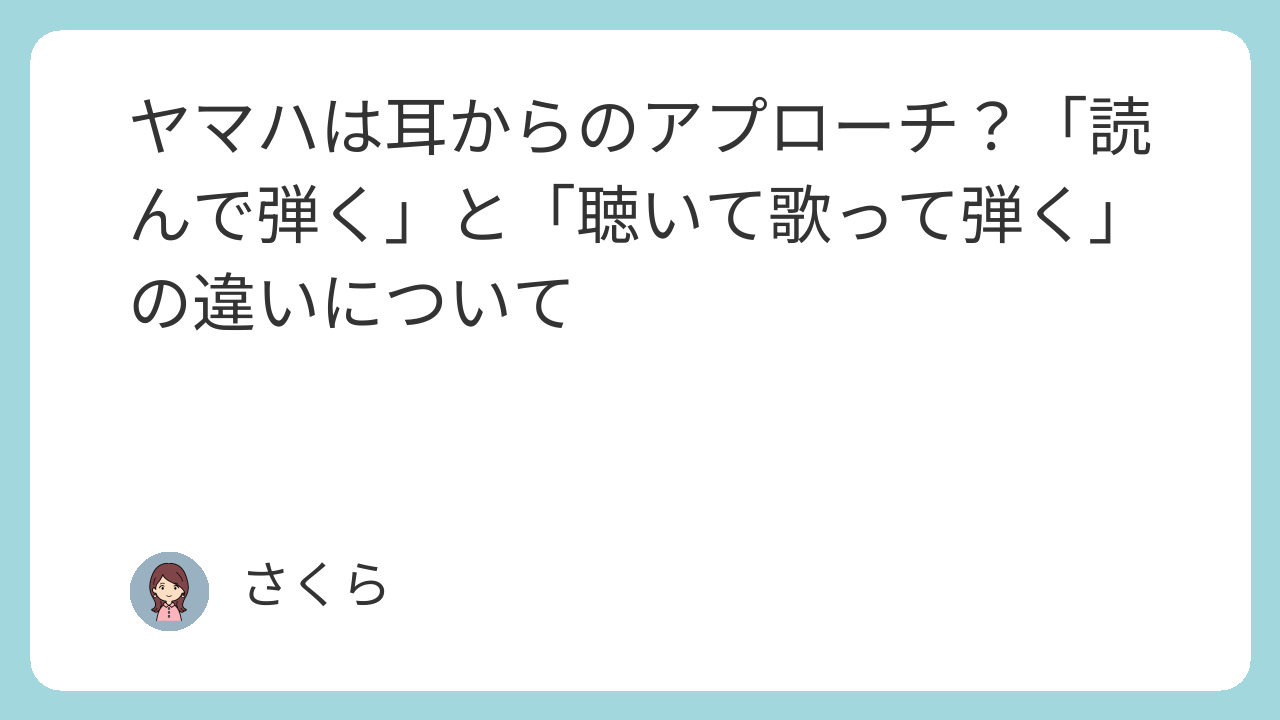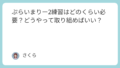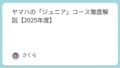ヤマハ音楽教室(YAMAHA MUSIC SCHOOL)のレッスンでは、適期教育(伸びる時期に伸びる力を伸ばす)を大切にしています。
耳の力が大きく成長する幼児期には、「耳から音楽を捉える力」を伸ばすことを大切にしたレッスンカリキュラムで学習します。
そのため、一般のピアノ教室では楽譜を読む→弾くという順番で取り組むことが多いところ、ヤマハでは聴いて歌ってそれから弾く、というレッスンになっています。
そうすることで何が違うのか解説していきます。
「きく→うたう→ひく」のレッスンでどんな力が身につくか
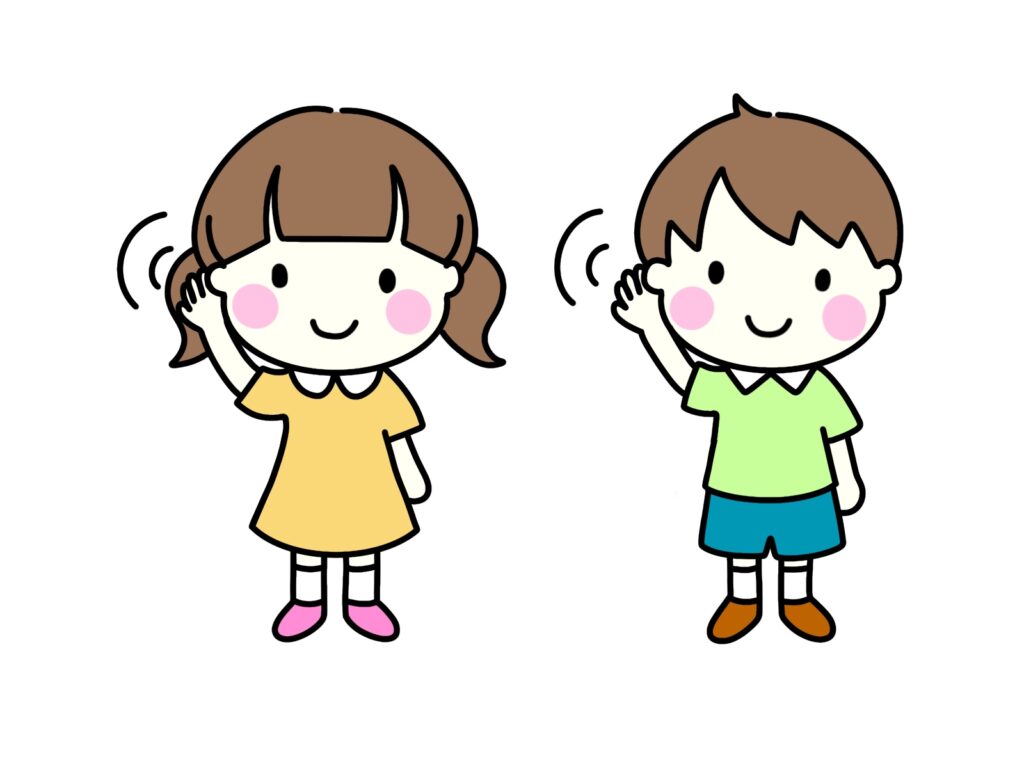
ヤマハ音楽教室の幼児期レッスン(ぷらいまりーや幼児科)では、新しい曲に取り組む際、「きく→うたう→ひく」の順でレッスンしていきます。
それぞれの段階でどんな力が身についていくのか紹介していきます。
「きく」ことはなぜ大切か
初めての曲に取り組む際、まずはCD・音源や先生の演奏を聴くところから始まります。
目からの情報ではなく、耳からの情報を頼りにして取り組むことは、幼児期の子どもたちにとって無理なく取り組める最適な方法です。
音楽ではなく言葉を例にとってみても、カタカナや漢字が含まれた文章をスラスラと読むことは難しくても、読み方が分かれば(大人がこうやって読むんだよと教えてあげれば)スムーズに話すことができると思います。
聴いて真似することが得意な時期には、その得意な力を上手く使って学習していくことで、楽しく力をつけることができるのです。
たくさん聴いて、曲のイメージを広げたり、メロディー以外の音にも耳を傾けて曲を把握したりすることで、弾くときにより豊かな表現ができるようになっていきます。
「うたう」ことで身につく力
ヤマハで弾く前に大切にしているのは歌うことです。
歌は、鍵盤の演奏よりも簡単にさまざまな表現をすることができます。
例えば、音の強弱。
鍵盤で演奏するには、指のコントロールが必要で、なかなかスムーズに出したい強さの音で弾くことができません。
歌であれば、ちょっとしたイメージで、大きな声・小さな声の歌い分け、さらにきれいな感じ、広がっていく感じ、軽い感じ、はっきりとした感じなど、さまざまな表現ができます。
歌で表現できることで、弾く際にも「こうやってひきたい」というイメージを持つことができ、指の力の成長と共に思うような表現ができるようになっていきます。
歌うことは表現の幅を広げていくことにつながっているのです。
「ひく」ときに意識していること
ヤマハのレッスンでは、歌った通りに弾くことを大切にしています。
歌で覚えた音楽と鍵盤で演奏する音楽を一致させることを通して、「感じたことを音にする」経験を積み重ねます。
鍵盤を弾く上で、楽譜の通りに指が動けば良いと思っている方もいらっしゃると思いますが、それだけでは素敵な演奏にはなりません。
音楽の持つさまざまなニュアンスを楽譜から読み解くのはかなりの経験が必要ですが、歌で表現することは比較的容易にできます。
その歌ったイメージのまま弾くことで、表情豊かな演奏表現につながっていきます。
幼児期(ぷらいまりー、幼児科)では、歌いながら弾くことが大切です。
覚えたドレミ、その音程、鍵盤の位置、イメージした表現、そして弾くときの指の感覚。全てを使って音感を育て、鍵盤把握の力をつけていきます。
児童期になると、レッスンで歌いながら弾く場面は減ると思いますが、
自分の弾くことを心の中で歌うこと、それだけでは意識が難しい場合は声に出して歌うことは引き続き大切です。
このような「きく→うたう→ひく」経験を通して、「音楽的に弾く」力を身につけていきます。
読んで弾くことのメリット・デメリット

一方の楽譜を読む→弾くレッスンでは、どのようなメリット・デメリットがあるのかまとめました。
よむ→ひく学習のメリット
楽譜を読んで弾くというレッスンの形のメリットは、楽譜を読めるようになるのが早いということです。
レッスンでもご家庭での練習でも、楽譜を読む→その音を弾くということを繰り返すため、楽譜を読む意識、楽譜通りに弾く意識を早い段階から持つことができます。
よむ→ひく学習のデメリット
楽譜通りに弾く意識を早い段階から持つことは、幼児期の場合デメリットでもあります。
一番大きなデメリットは「自分の弾いた音をよく聴く意識が持てない」ことです。
よむ→ひくの学習では、楽譜を正しく読めたこと、それを弾けたことを評価されることが多いです。
そのことで、「楽譜通りに指が動けば良い」と思ってしまうお子さんも多いです。
その習慣で弾き続けてしまうと、抑揚がない演奏、不自然なテンポの揺れがある演奏、乱暴な音色の演奏など、音楽的ではない演奏につながってしまう場合があります。
よむ→ひく学習の場合も、自分の音をよく聴くことはとても大切なのです。
【まとめ】幼児期には耳からのレッスン、小学生からは目と耳のバランスの良い学習を

以上のことから私は、幼児期にはきく→うたう→ひくのレッスンが最適と思っています。
小さい頃に自分の音をよく聴く意識、歌心を持って弾く意識を自然と身につければ、
大きくなって読む→弾くときにも自分の音をよく聴き、どのような表現が良いか感じながら演奏できるようになります。
一方、小学生からは耳の力とドレミを読むことのバランスを取りながら学習していくことが大切です。児童期のソルフェージュ学習を通して、楽譜から曲の表情を読み解く、そしてそれを表現できる力につなげていきたいと思っています。
幼児科・ぷらいまりーから上がった小学生の練習のやり方、力のつけ方はこちらで解説しています。よかったらご覧ください。